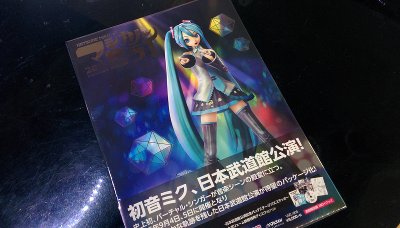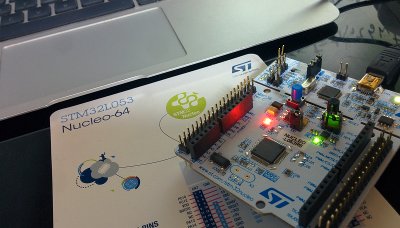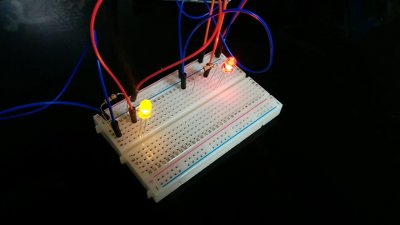2月頭からちまちま組んでいたKSR110がようやく走れる段階になったのでまとめ
競技志向で1年過ごしてみて、やはり経済的に厳しいなーという事で乗り替えを決意したのが年明けあたり。
色々検討してみたけど、たとえ排気量を下げたとしてもタイヤが17インチである限りそれほどコストが下がらない事がわかった。
ということでターゲットはミニに絞る。
タマ数豊富で、乗り出しが安くて、ノウハウが多い・・・
という事でターゲットは4ストKSRに決定!
2ストもすごく興味があったんだけど、今回はコスト最重要視のため4ストで。
ヤ◯オクをウォッチすると、クラッチ装着済みの車両が近場で出ていたのでさっそく現車確認。
外観はかなり残念だけどエンジン始動は問題なし。
単気筒ならまあどうにかできるだろうという事で、落札。
自宅ガレージにて整備作業開始。
フォークとブレーキはオーバーホール。
ホイールは純正アルミを投入。
マフラーはこれまたオクでおとした中古WR’S。
タイヤはTT93GPソフトを新品で。(とりあえず前後純正サイズ)
サビサビだったリアサスは武川(新品で1万円以下)に。
サス交換のついでにスイングピボットのグリスアップも
と思ったものの、どうしてもスイングアームのシャフトが抜けない・・・
休日に郊外まで持って行きハンマーでシャフトを叩きまくったけど1ミリも動かず・・・
ネットで検索してみると、古めのKSRではメジャーな事例らしく・・・
油圧プレスで抜いたとかスイングアームごと切断したとかいうヘビーな事例がゴロゴロ。
こりゃセルフ作業では無理だ、という事でトップウェイ守口店さんに作業を依頼。
結局スイングアーム破壊にて対処してもらう事となりました。

その後は別途入手した中古スイングアーム(KSR PRO用っぽい)を装着。
KSRは中古部品も豊富でいい!
ピボット部分はニードルベアリングも仕込まれており、いい感じ!
一通りの整備が終わり、試走も完了。
早速、練習会で本番投入!

第一印象は
「遅い・・・」
650と比べるのは酷ってもんだけど、スタートダッシュでの圧倒的パワー不足感はにっちもさっちも。
ステップが低すぎて、ちょっと寝かすとすぐガリガリ。
前ブレーキがプア。
ポジションの自由度が高すぎてどこに座っていいかわからない。
ハンドル切れすぎ(これは調整すればなんとかなりそう)
ネガばかりという訳ではなく
バランスを崩してもむりやり立て直せてしまう圧倒的な軽さ
体がついていかないくらいの回転半径の小ささ
ノーマルのパワーでは滑る気配すら無いタイヤ(TT93GP)の安心感
といった要素もあるので今しばらくは乗り込んでみようと思います。